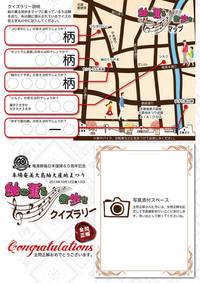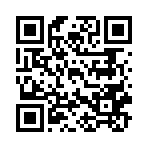2012年08月10日
大島紬の「泥染め」
南です。
今朝早起きしてなでしこJAPAN応援しましたが惜しくも銀メダルでしたね。
渡英してた常田氏も本日日本に戻りましたのでいろいろと話をきいて順次報告したいと思います。
さて今日は大島紬の「泥染め」について。
現在泥染めだけではなく様々な染色方法で作られていますが、やはり大島紬の代表する染めは「泥染め」。
奄美での染めの歴史は古く、昔の文献に「茶褐色の絹織物が献上された」という文が残っていたそうで、おおよそ1300年くらい前からあるといわれています。
はっきりとした起源は分かりませんが、テーチ染めをした着物を役人の目に届かないよう泥田に隠したところ次の日に黒くなってたといういわれもあります。
テーチ木染めをして茶褐色に染まった糸を泥田の中で染めていくとテーチ木に含まれていたタンニン酸と泥の中の鉄分が化学反応を起こし、黒褐色に染まっていきます。

理論的には鉄分を含む溶液で染めても染まるはずですが、日本全国どこの泥田でも染まるわけではありません。
もちろん鉄分を多く含み、粒子が細かい奄美の奄美の泥じゃないと染めることができないのです。
粒子が粗いと糸を痛め毛羽立ちや糸切れの原因となってしまいます。
このあと川へ行き、余分な泥を落として乾燥の後、またテーチ木染めと泥染めとを繰り返していきます。
余談ですが、泥田の鉄分が少なくなるとソテツの葉を細かく刻んで沈めておくとまた鉄分が回復するようです。
ソテツ・・・漢字で書くと「蘇鉄」なるほど。。。
大島紬の「加工」へ続く。
今朝早起きしてなでしこJAPAN応援しましたが惜しくも銀メダルでしたね。
渡英してた常田氏も本日日本に戻りましたのでいろいろと話をきいて順次報告したいと思います。
さて今日は大島紬の「泥染め」について。
現在泥染めだけではなく様々な染色方法で作られていますが、やはり大島紬の代表する染めは「泥染め」。
奄美での染めの歴史は古く、昔の文献に「茶褐色の絹織物が献上された」という文が残っていたそうで、おおよそ1300年くらい前からあるといわれています。
はっきりとした起源は分かりませんが、テーチ染めをした着物を役人の目に届かないよう泥田に隠したところ次の日に黒くなってたといういわれもあります。
テーチ木染めをして茶褐色に染まった糸を泥田の中で染めていくとテーチ木に含まれていたタンニン酸と泥の中の鉄分が化学反応を起こし、黒褐色に染まっていきます。
理論的には鉄分を含む溶液で染めても染まるはずですが、日本全国どこの泥田でも染まるわけではありません。
もちろん鉄分を多く含み、粒子が細かい奄美の奄美の泥じゃないと染めることができないのです。
粒子が粗いと糸を痛め毛羽立ちや糸切れの原因となってしまいます。
このあと川へ行き、余分な泥を落として乾燥の後、またテーチ木染めと泥染めとを繰り返していきます。
余談ですが、泥田の鉄分が少なくなるとソテツの葉を細かく刻んで沈めておくとまた鉄分が回復するようです。
ソテツ・・・漢字で書くと「蘇鉄」なるほど。。。
大島紬の「加工」へ続く。